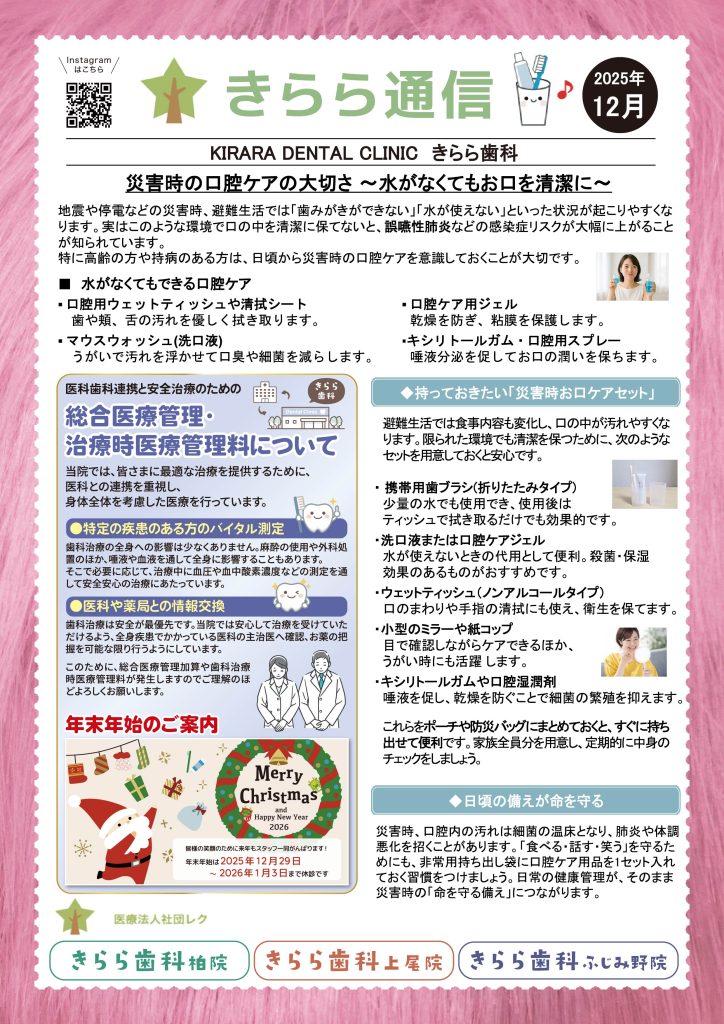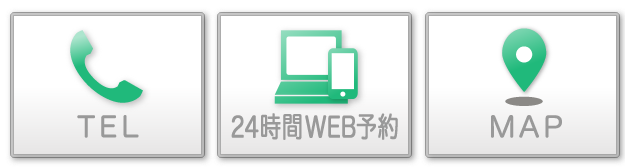きらら通信
災害時の健康リスクを減らすために口腔ケアが欠かせない理由
こんにちは。
ベイシア上尾平塚内の歯医者、きらら歯科上尾院です。
今回は、災害時に口腔ケアがなぜ大切なのかについてご紹介します。
大きな災害が起こると、水道や電気が止まり、普段のように歯みがきができない状態が続くことがあります。避難所生活では水を節約する必要があり、歯を磨くために水を使うことにためらいを感じる方も少なくありません。その結果、お口の中に汚れが残りやすく、細菌が増えやすい環境になります。またストレスや食生活の変化により、唾液量が減ってしまうこともあり、これも細菌が増えやすくなる大きな要因です。
口の中が不衛生になることで起こる問題
口腔内の清掃が十分に行えない状態が続くと、細菌が増えることで口臭や歯ぐきの腫れが起こりやすくなります。特に避難時は食事の内容が偏り、柔らかいものや糖質の多い食品が続くことも多く、汚れが残りやすい環境になりがちです。また、歯周病菌が増えると全身への影響も見逃せません。特に高齢者では誤嚥性肺炎のリスクが上昇するため、災害時の口腔ケア不足は深刻な健康トラブルにつながりかねません。基礎疾患のある方にとっても、口腔内の細菌増加は持病の悪化につながる場合があります。
限られた環境でも続けられるケアの方法
災害時でも、工夫次第でお口を清潔に保つことができます。例えば歯ブラシがあれば、水がなくても乾いたまま磨いて汚れを落とし、最後に少量の水でゆすぐだけでも効果があります。また、歯みがきシートやウェットティッシュで歯の表面を拭う方法も、お口の中の清掃として十分役立ちます。唾液を増やす目的でキシリトールガムを噛むことも、細菌の繁殖を抑える助けになります。大切なのは「できる範囲で続けること」であり、完璧に磨けなくても、少しでも清潔を保つ工夫をしていくことが重要です。
まとめ
災害時に困らないためには、日常的に必要最低限の口腔ケア用品を準備しておくことが大切です。特別なものを多く揃えなくても、普段使いのものを少し余分に備蓄しておくだけでも安心感が大きく変わります。また、平常時から歯科医院でのメンテナンスを継続し、歯ぐきの状態やむし歯のリスクを下げておくことは、非常時のトラブルを減らすための大きな助けになります。どんな状況でも健康を守るために、日頃からお口のケアを意識しておくようにしましょう。
きらら通信1月号です
こんにちは! 医療法人レクきらら歯科です!
医療法人レクでは毎月「きらら通信」 を発行しています
1月は『お口の乾燥と唾液のチカラ』についてです。
詳しく知りたい方はお気軽にスタッフにお声かけください!
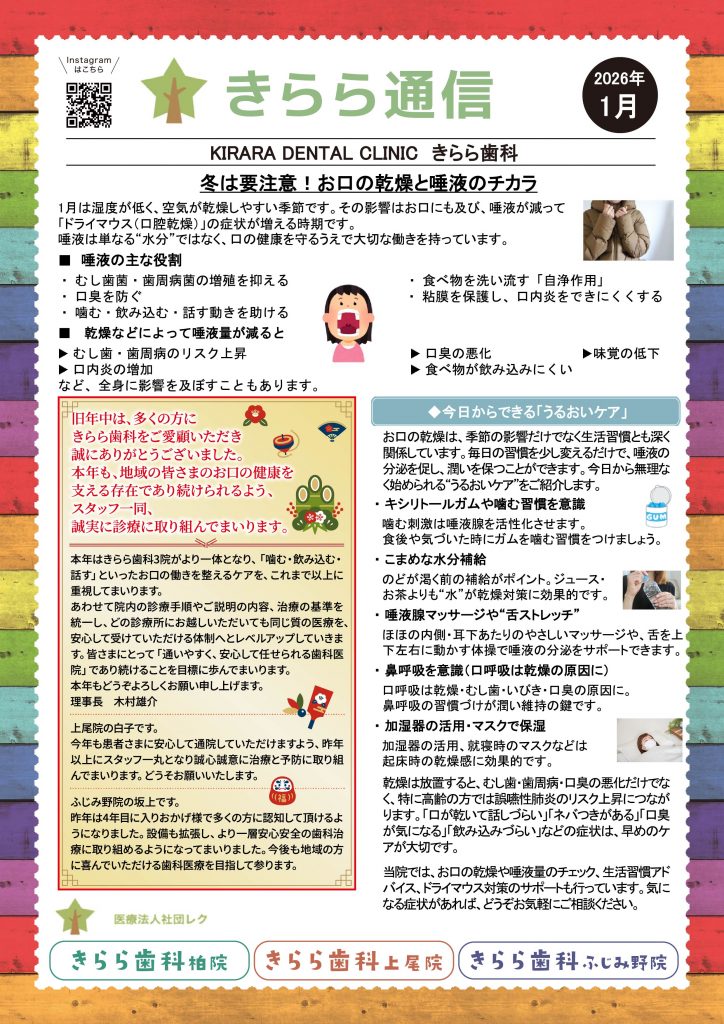
顎の痛みを繰り返さないために セルフケアと歯科サポートで整える
こんにちは。
ベイシア上尾平塚内の歯医者、きらら歯科上尾院です。
今回は、顎関節症のセルフケアと歯科で受けられるサポートについてお話しします。顎の痛みやカクカク音、口の開けづらさといった症状は、放っておくと悪化してしまうこともあります。ですが、正しいケアと治療を組み合わせることで、多くの場合は改善が期待できます。初期のうちに対処することで痛みの慢性化を防ぎ、日常生活の快適さを取り戻しましょう。
ご家庭でできるセルフケア
顎関節症の予防・改善には、毎日のちょっとした意識が大切です。まず意識したいのが、「歯を離してリラックスすること」。上下の歯が常に触れている状態は、顎関節や筋肉を疲れさせてしまいます。普段から「唇は閉じて、歯は離す」が理想です。パソコン作業やスマートフォン使用時など、無意識に力が入る場面では特に注意しましょう。
次に、筋肉を温めるケアを取り入れましょう。蒸しタオルを頬やこめかみにあてると、血流が良くなり、顎の筋肉がやわらぎます。痛みを感じるときにもおすすめです。軽いストレッチやマッサージも効果的です。口を無理なく開閉したり、頬の筋肉を円を描くように指でほぐすと、こりの解消につながります。就寝前のリラックスタイムに取り入れると、翌朝の顎のこわばりが軽くなることもあります。
また、硬い食べ物を避けることも重要です。ガムやスルメ、フランスパンのような噛みごたえのある食品は、顎への負担を増やします。さらに、姿勢も忘れずに。背筋を伸ばして座り、顎を引くことで関節への負担が軽くなります。猫背やうつむき姿勢は、顎の位置をずらし、痛みの原因になることがあります。
歯科で受けられるサポート
セルフケアを行っても改善しない場合は、歯科医院を受診しましょう。歯科では、噛み合わせの状態を細かくチェックし、必要に応じてマウスピースを作製します。これにより、就寝中の歯ぎしりや食いしばりから顎関節を守ることができます。マウスピースは顎への負担を均一に分散させ、筋肉の緊張をやわらげる効果もあります。
炎症が強い場合には、痛み止めや筋肉をやわらげるお薬が処方されることもあります。症状の原因が複雑な場合や再発を繰り返す場合は、顎関節症専門医での診察が有効です。歯科での継続的なフォローにより、日常生活の中での注意点も具体的にアドバイスを受けることができます。
まとめ
顎関節症は再発しやすいトラブルですが、正しいケアで大きく予防することができます。「歯を離して」「温めて」「姿勢を整える」という3つのポイントを意識しながら、顎に優しい生活を心がけましょう。症状を軽く見ず、早めに専門的なサポートを受けることが大切です。日々の小さな積み重ねが、将来の顎の健康を守ります。違和感が続くときは無理せず、お気軽にご相談ください。
「なんとなく顎が痛い」それは季節の変わり目のサインかも?
こんにちは。
ベイシア上尾平塚内の歯医者、きらら歯科上尾院です。
今回は、季節の変わり目に気付きやすい「顎関節症」についてお話ししていきます。寒くなり始める11月、体の不調を感じる方が増えます。その中でも、意外と多いのが「顎の違和感」です。「口を開けると痛い」「食事中に顎が鳴る」「朝、顎が疲れている」などの症状が出ている方は、もしかすると顎関節症かもしれません。
顎関節症とは?
顎関節症は、顎の関節や筋肉に負担がかかることで起こるトラブルです。顎を動かすたびにカクッと音がしたり、痛みを感じたり、口を大きく開けられなくなるなど、症状はさまざまです。悪化すると硬いものを噛めなくなったり、顎の動きが制限され、会話や食事に支障をきたすこともあります。
特に、若い女性やストレスの多い方に多くみられる傾向があり、最近では小中学生でもスマホやゲーム中の姿勢の影響で発症するケースも増えています。放置してしまうと、慢性化しやすく回復までに時間がかかるため、早期の気づきが大切です。
季節の変わり目に注意が必要な理由
寒さや気温差は、体の筋肉をこわばらせる原因になります。顎の筋肉も同じで、冷えによって血行が悪くなると、筋肉が硬くなり痛みが出やすくなります。さらに、寒暖差による自律神経の乱れで睡眠の質が落ちたり、ストレスが増えたりすることで、無意識の歯ぎしり・食いしばりが増加します。これが顎関節に大きな負担をかけ、症状を悪化させるのです。
また、寒くなると肩をすくめる姿勢が増え、首から顎にかけての筋肉が緊張しやすくなります。その影響で顎の可動域が制限され、痛みや音が出やすくなることも。さらに、乾燥した空気による体の緊張や、日照時間の減少によるストレスの増加も、症状を誘発する一因と考えられています。
放置してはいけない理由
「痛いけど我慢できるから」と放っておくと、顎関節症は徐々に進行します。関節円板がずれて関節音が強くなり、最終的には口が開かなくなる「ロッキング」状態になることも。また、顎の不調は首・肩・頭などの筋肉にも影響を及ぼし、肩こりや頭痛、耳鳴り、めまいといった症状を引き起こすことがあります。噛み合わせのバランスが崩れると、顔の左右差や歪みが出ることもあるため、早期の対処が重要です。
さらに、顎関節症を放置すると、痛みを避けるために偏った咀嚼をするようになり、片側の筋肉だけが発達してしまうことも。これにより顔の形が変わる、姿勢が歪むといった二次的な問題を引き起こすケースも少なくありません。顎関節の異常は全身のバランスに関係するため、単なる「顎の不調」と侮れないのです。
まとめ
顎関節症は、早めの診断と適切な対応で改善が期待できる病気です。寒暖差を感じるこの季節、「なんとなく顎が変」と思ったら、そのままにせず歯科医院にご相談ください。体も心もストレスを感じやすい時期だからこそ、顎の健康を整えて毎日を快適に過ごしましょう。
きらら通信12月号です
こんにちは! 医療法人レクきらら歯科です!
医療法人レクでは毎月「きらら通信」 を発行しています
12月は『災害時の口腔ケアの大切さ』についてです。
詳しく知りたい方はお気軽にスタッフにお声かけください!